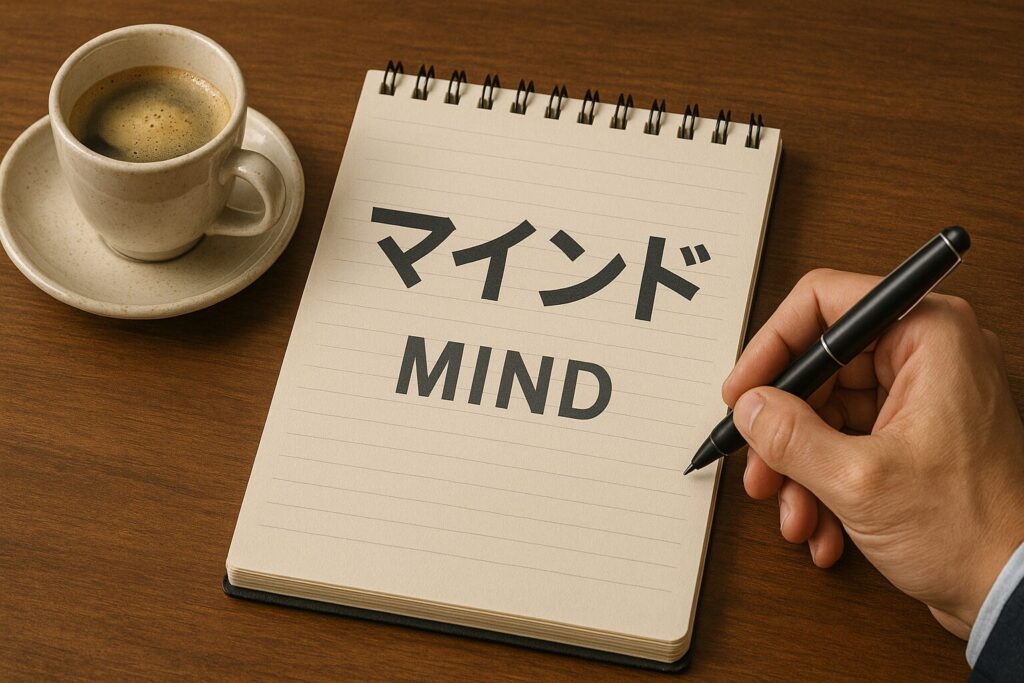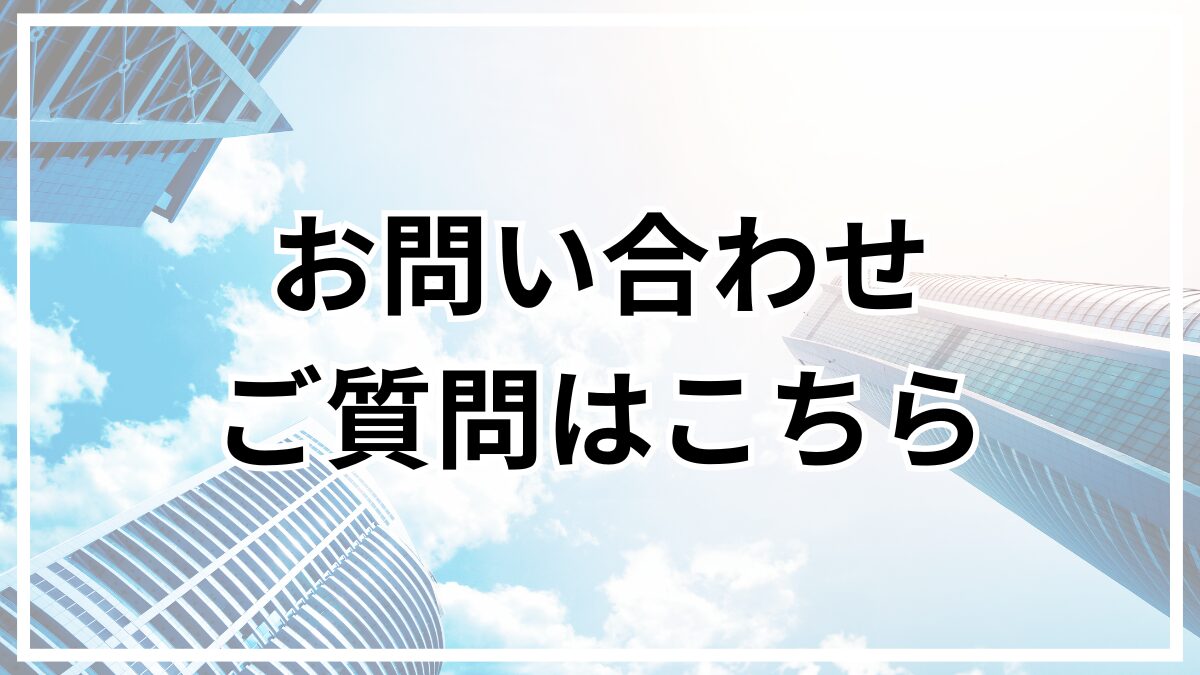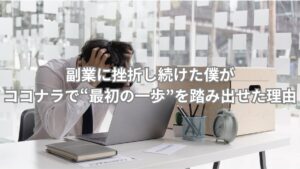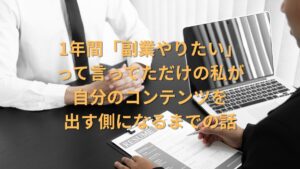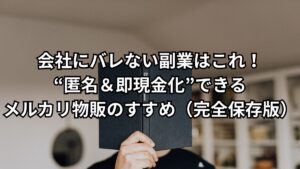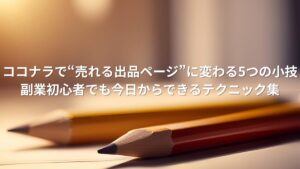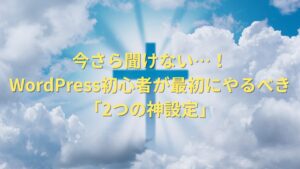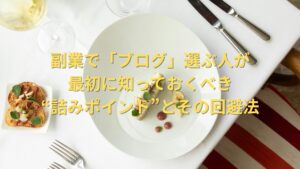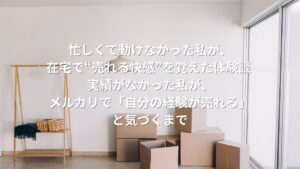【2025年最新版】アドセンス審査が通らないのは「中身のせい」じゃなかった 合格を分けるのは、“記事”ではなく“導線設計”だった話
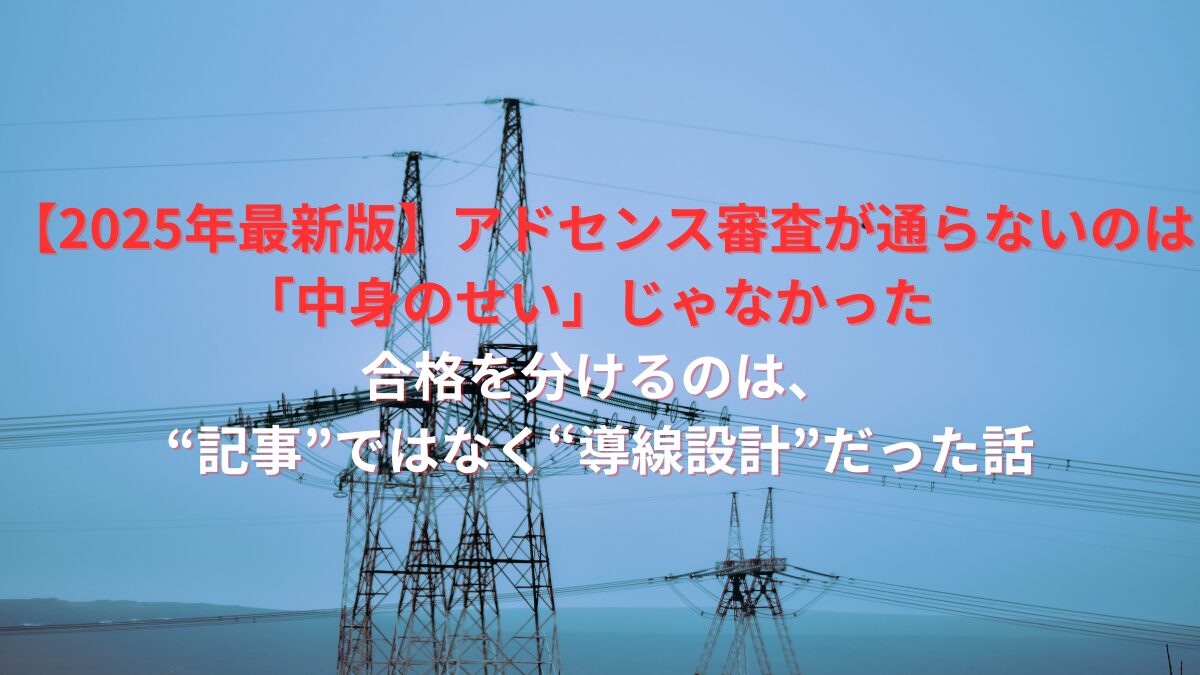
 セハム
セハムまた落ちた。
通知を見た瞬間、
体の中の何かが、ストンと音を立てて落ちていく感じがしたんですよね。
たしかに、今回もちゃんと準備してたんです。
記事数も揃えたし、プロフィールも書いた。
お問い合わせやプライバシーポリシーも忘れずに設置した。
「今回はいける」
そう思っていたはずなのに、結果はまた不合格。
そしてまた、例のセリフが浮かびます。
「なんで?」
「何が足りなかったんだろう…」
気づけば、何度も繰り返しているこの問答。
そのたびに修正し、また挑んで、でもまた落ちる。
でも、ある時ようやく気づいたんです。
「自分が見ていた場所そのものがズレていた」ことに。
記事の中身じゃない。
プロフィールの書き方でもない。
ポリシーページの有無でもなかった。
合格を分けていたのは、
「読者をどこへ導くか?」という視点の有無でした。
この記事では、僕がアドセンス審査に3度合格した中で見えてきた
“突破の設計図”をすべて言語化します。
テンプレを試しても通らなかった人
ChatGPTで記事を書いても不合格だった人
もう理由がわからなくなって諦めかけてる人
そんなあなたのために、
「構造から設計しなおす」という、
ちょっとだけ視点をズラした合格法をお伝えします。
ではまずは、ここから始めましょう。
「また落ちた…」から始まる物語


通知を見た瞬間、
思わずモニターの前で天を仰ぎました。
またか……
もう、何回目の不合格だったかは正直覚えていません。
でもひとつだけ言えるのは、
毎回「今度こそは」と思って、ちゃんと準備していたということです。
・記事数は十分に用意した
・プロフィールも丁寧に書いた
・お問い合わせフォームやポリシーページも漏れなく設置した
それでも、毎回「不合格」の通知が届く。
「何が足りないんだ?」
「これでダメなら、どうすればいいんだ…」
そんな風に思っては、また手直しして、
再申請して、また落ちる
いつの間にか、そんなループにハマっていました。
正直、
心が折れそうになる瞬間は何度もありました。
でも今なら、はっきりわかります。
当時の僕は、“見る場所”そのものを間違えていたんです。
記事の中身や文法、画像の有無にばかり目を向けていたけれど、
本当に見なければいけなかったのは「構造」でした。
“中身の質”ではなく、“ブログ全体の流れ”が見られていたんです。
記事単体でどれだけ丁寧に書かれていても、
全体がバラバラなら、読者は迷子になります。
そして、
その“迷子感”こそが、審査で落ちる最大の原因でした。
「記事が良くないからダメなんだ」
「ChatGPTだから伝わらないのかも」
「画像が少なかったから?」
そうじゃなかった。
もっと根本的に、「読者をどう導くか」という視点が抜けていたんです。
この気づきにたどり着いてから、
僕のアドセンス戦略はガラッと変わりました。
そしてようやく、
“合格の本質”にたどり着くことができたんです。
テンプレ信仰が通用しなくなった時代
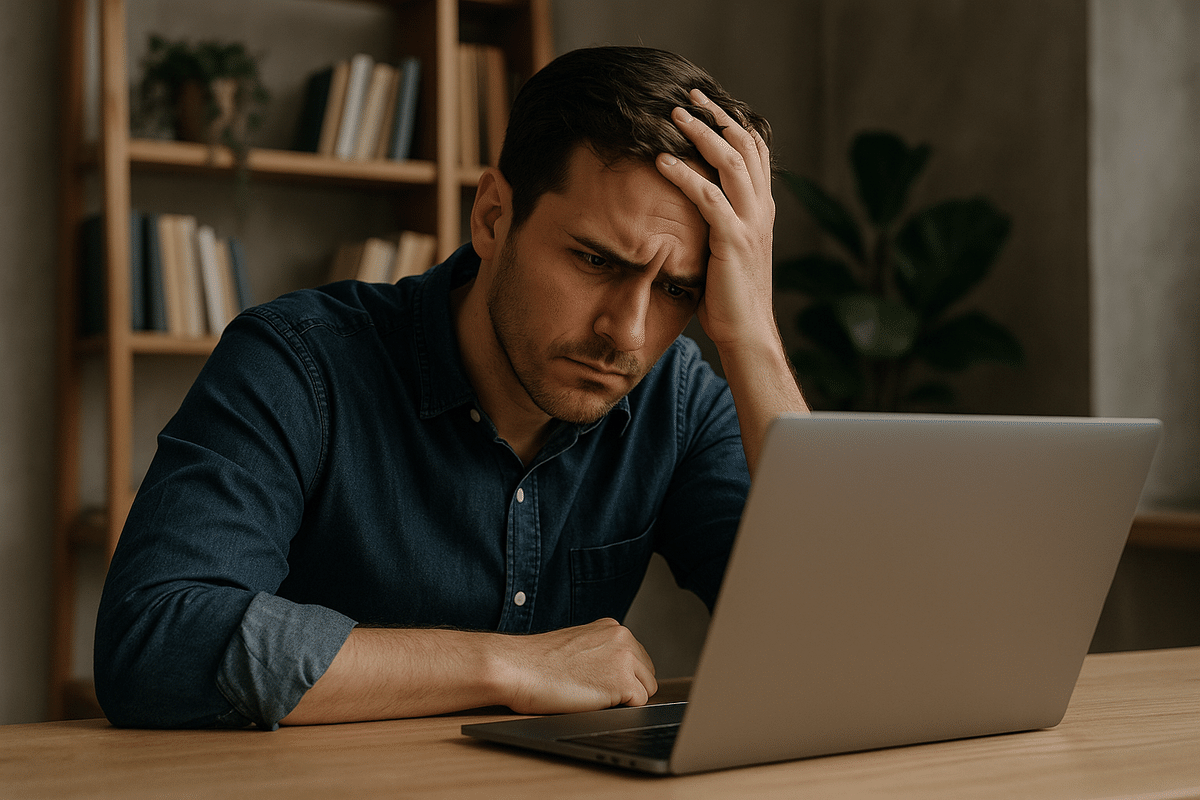
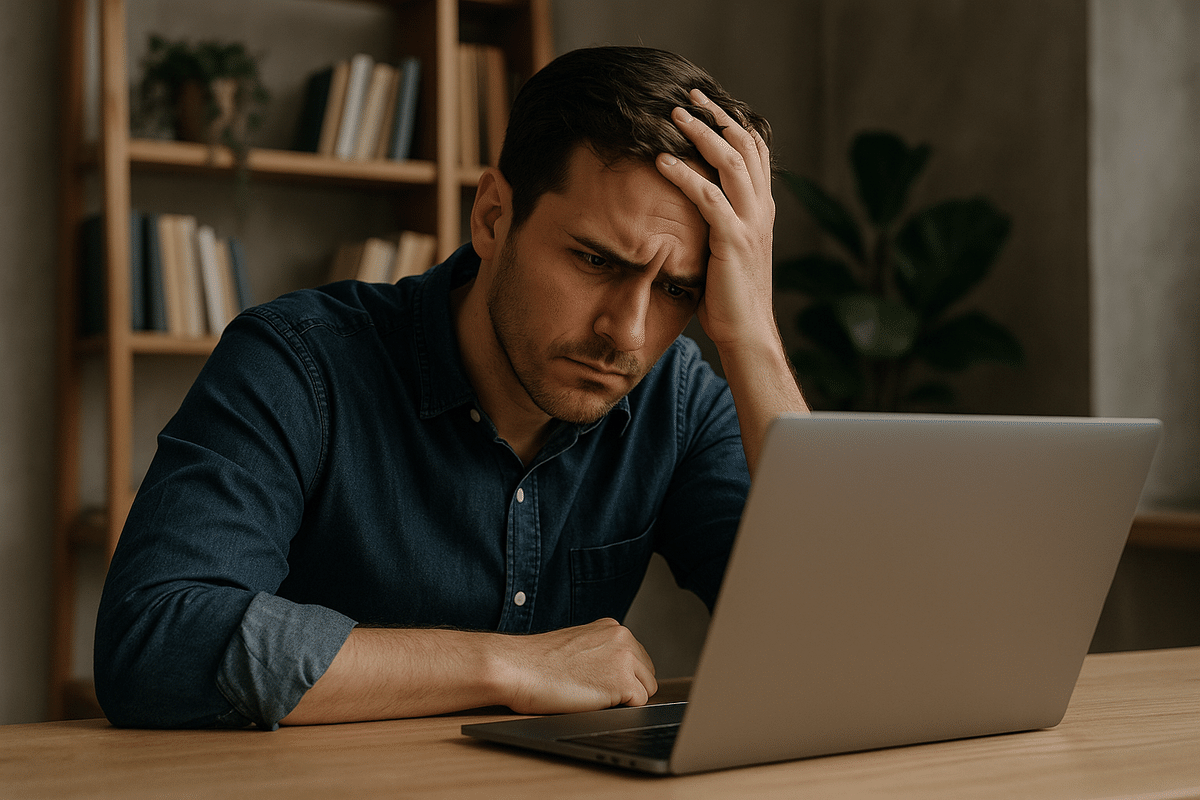
「アドセンスなんて、テンプレ通りやれば通る」
そんな時代が、たしかにありました。
僕自身も過去にそのやり方で合格した経験があります。
記事数を揃える。
プロフィールを丁寧に書く。
問い合わせフォームとポリシーページを設置する。
内容は日記でもOK。ジャンルは何でもOK。
そう言われていた頃です。
でも、2025年の今。
昔の成功法則は、もう通用しないんですよ。
同じように準備して、同じように構成して、
それでも通らない。何度やっても、不合格。
「前と同じようにやったのに、なぜ?」
最初は、その理由がまったくわかりませんでした。
でもあとになって冷静に考えてみると、
ある変化に気づいたんです。
アドセンスの審査が、“人の目”で行われている可能性が高まっている。
「いやいや、AIがチェックしてるんじゃないの?」
そう思うかもしれません。
たしかに一部はAIかもしれない。
でも、最近の審査はあまりにも“人間らしい視点”が反映されすぎている。
✔ デザインだけ整った薄っぺらいサイト
✔ 記事同士の繋がりがまったくない構成
✔ 誰に向けて書かれているか不明な文章
そういう「作り込みの浅さ」が、
審査の段階で容赦なく見抜かれている感覚があります。
これは、たまたまではなく、明確な変化です。
「中身」ではなく「読者視点での構造」が見られている。
つまり
「テンプレ通りに整えておけばOK」という考えは、
もはや時代遅れなんです。
そしてこの視点に気づけていない限り、
どれだけ修正しても、同じ場所をグルグルと回るだけ。
これは僕自身が、まさにそうだったからこそ痛感している事実です。
テンプレ信仰は、ある意味で“思考停止”を生みます。
言われた通りやっていれば通ると思い込んでしまうから。
でも、今の審査はもっと厳しい。
もっと“読み手の動線”を重視する構造的な目線でチェックされている。
そしてそこに気づかない限り、
いくら「記事数」や「文字数」を増やしても、結果は変わりません。
「テンプレでは通らない時代になった」
この言葉を、今だからこそ強くお伝えしたいんです。
記事のクオリティではなく“構造”が見られている
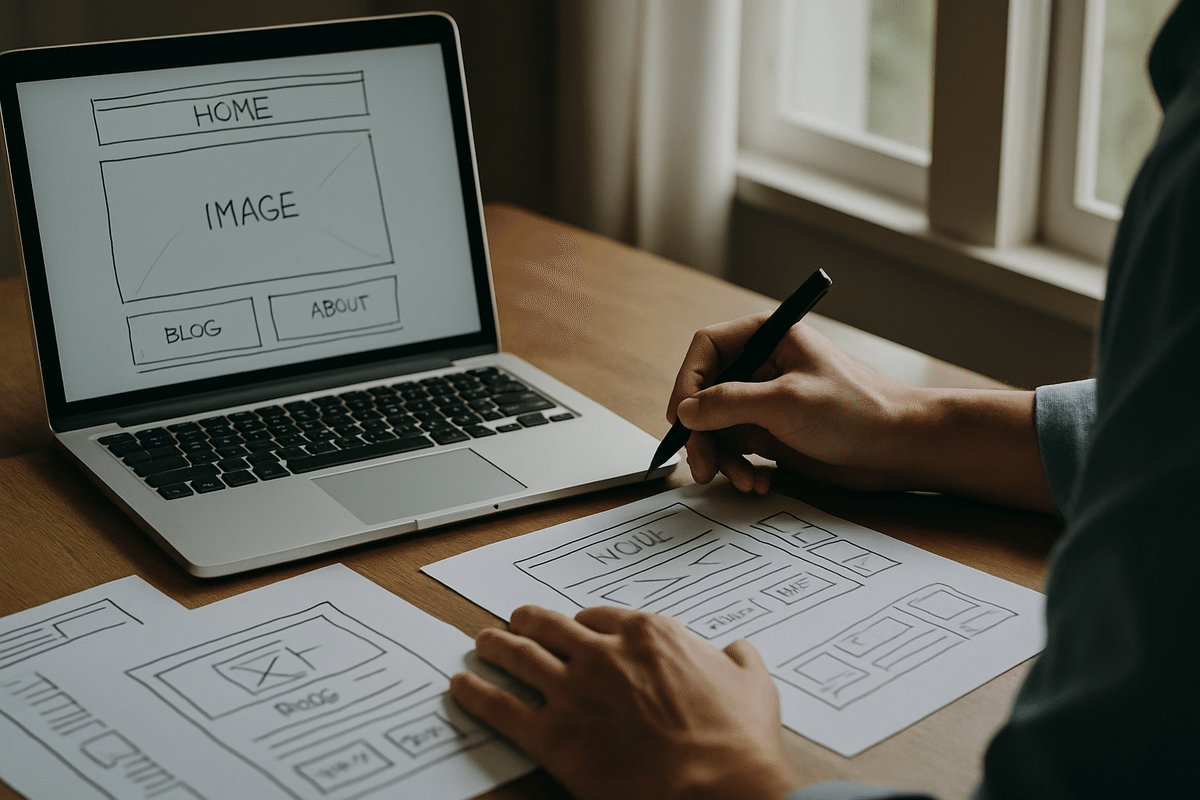
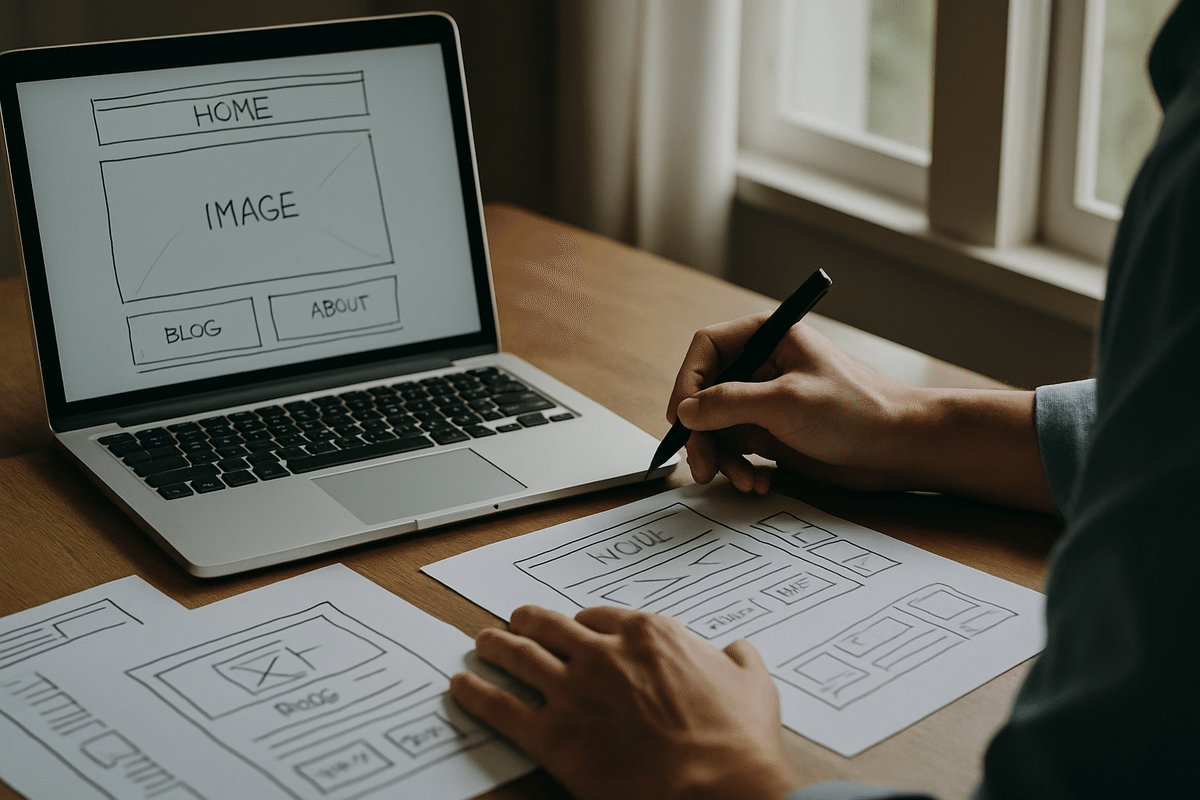
アドセンス審査でつまずいていた頃、
僕はずっと「記事の中身」にこだわっていました。
誤字脱字をなくす。
情報の正確性を保つ。
文字数をしっかり確保する。
写真や見出しを整える。
「ここまでやれば大丈夫だろう」
そう思って申請するたびに、不合格の通知が届く。
……何度繰り返しても同じ結果。
正直、理解できなかったんですよね。
でも、あるときハッと気づきました。
見られているのは「記事そのもの」じゃなく「ブログ全体の流れ」だった。
例えば、
どれだけ1本の記事が分かりやすくても、
他の記事との繋がりがなければ、読者は行き場を失います。
✔ このサイトは誰のためにあるのか?
✔ どこから来た読者を、どこに導きたいのか?
✔ 全体を通して“ストーリー”が成立しているか?
こうした「設計の視点」が抜け落ちていると、
記事単体がどれだけ整っていても、評価されにくい。
つまり
文章のクオリティよりも、サイト全体の“構造”が問われていたんです。
僕が当時、何よりも見落としていたのはここでした。
審査する人の立場になれば当然ですよね。
バラバラの記事が並んでいるだけのブログに、
広告を載せたいと思うか?という話です。
「記事の完成度」ではなく「読者をどう動かすか」。
そこが抜けている限り、
どんなに頑張っても“不合格”を繰り返すことになります。
そして、この事実に気づけるかどうかが、
アドセンス突破の分かれ道なんだと思います。
ChatGPTの落とし穴と、僕が見逃していた視点
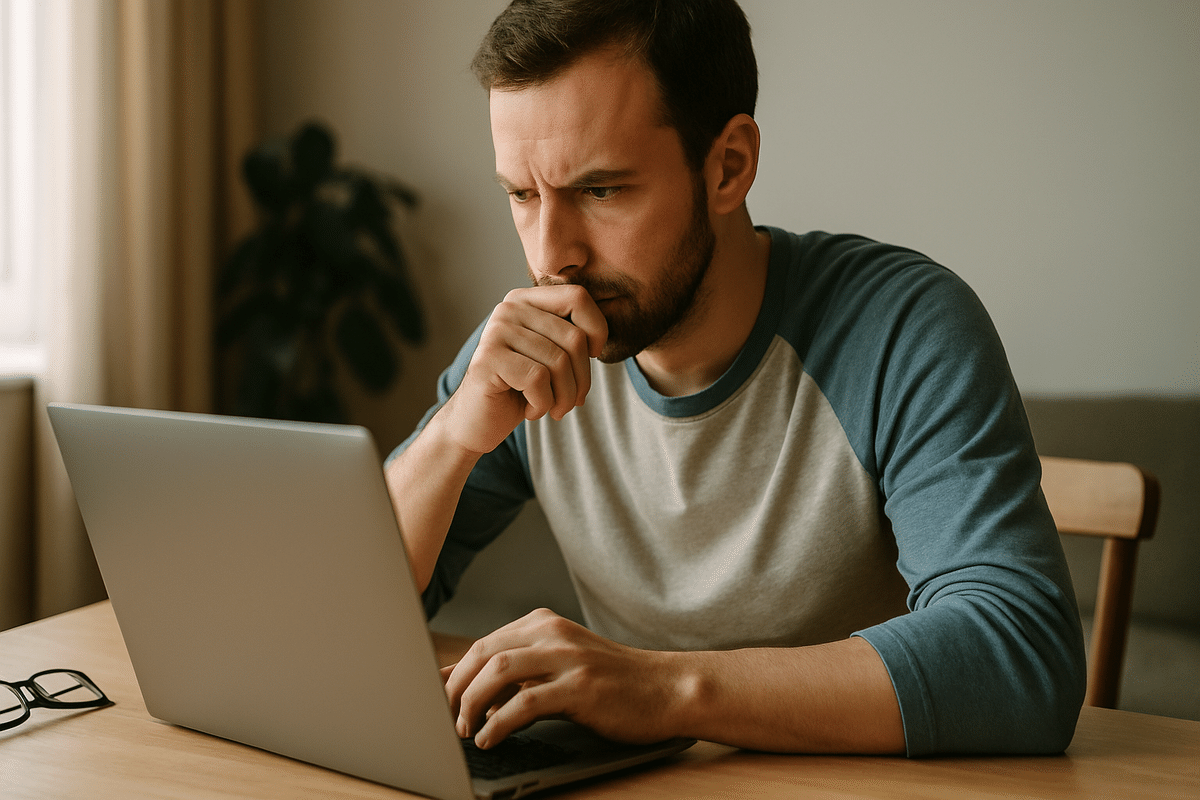
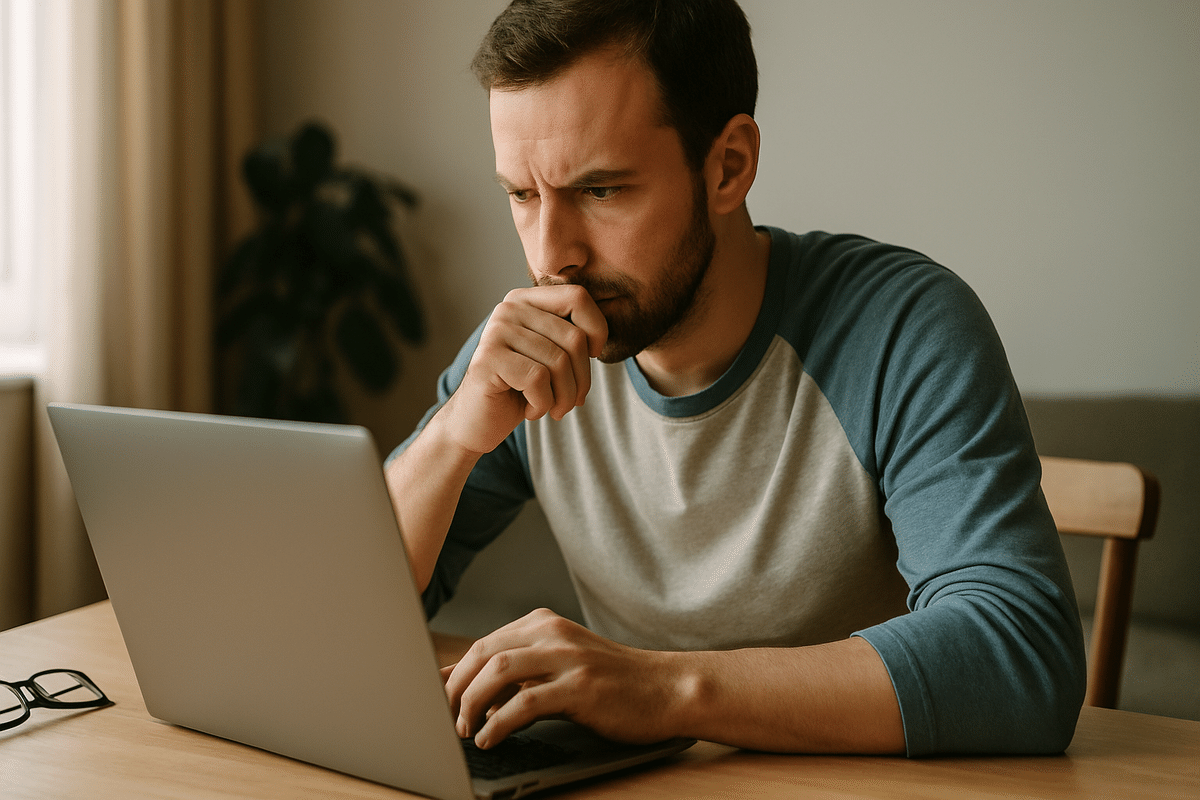
実は僕も最初の頃、ChatGPTを積極的に使って記事を書いていました。
構成は整っているし、文章の流れも自然。
「これはいける」
そう思って迷わず審査に出したんです。
でも結果は・・・やっぱり不合格。
正直、そのときは納得できませんでした。
誤字もない。情報も正しい。文字数だって十分ある。
「これで落ちるなら、もう理由なんて分からない」と思ったんですよね。
けれど、改めて冷静に自分のブログを見直してみると、
そこに致命的な“抜け”があることに気づいたんです。
「どこから来た読者が、どこへ進むのか」という流れを設計していなかった。
記事は1本1本で完結している。
でも、それ以上のつながりがない。
つまり、読者が次に何を読めばいいのか、どんな行動を取ればいいのか、
その道筋がまったく用意されていなかったんです。
ChatGPTはたしかに便利です。
でも、その出力を「並べるだけ」で終わらせてしまうと、
記事の“点”は増えても、全体を結ぶ“線”が存在しないサイトになる。
その事実に気づいたとき、心の中でこんな言葉が浮かびました。
「ああ、見られていたのは“中身”じゃなく、“流れ”だったんだ…」
この瞬間から、僕の戦略は大きく変わりました。
「記事をどう書くか」ではなく、
「記事同士をどうつなぐか」。
ここに意識をシフトさせたことで、
審査への向き合い方がまったく別物になっていったんです。
アドセンス審査で落ちるブログの“構造ミス”3選


僕が試行錯誤の中で気づいたのは、
アドセンス審査で不合格を繰り返すブログには、
ある“共通の構造的な欠陥”があるということです。
大きく分けると、この3つ。
① 記事を“単体”で考えてしまっている
多くの人は、記事1本ごとに「完成させる」ことを意識します。
もちろん、それ自体は大切です。
でも、アドセンスが見ているのはブログ全体の設計です。
記事単体だけを見ても、読者からすれば「このサイトって結局何がしたいの?」と感じる。
ストーリーのない記事群では、いくら中身がよくても“伝わらない”んです。
② アクセスの入り口が雑
SEOやSNS流入を意識している人は多いと思います。
でも「どんな人が、どんな目的でここに来るのか?」を設計していないケースがほとんどです。
その結果、記事内容と読者のニーズが噛み合わない。
さらに審査担当も「誰向けのサイトなのか」が分からないまま、そっとページを閉じてしまうんですよね。
③ 「読者をどう動かすか」の設計がない
記事を読んでも、その後どうすればいいのか分からない。
次に読む記事もなければ、行動への導きもない。
これでは、せっかく記事の内容がよくても“ただ読まれて終わり”になります。
アドセンスの合否に直接関係がなくても、
読者に「次の動き」が見えるブログは、審査側にも好印象を与えます。
つまり
記事単体の出来ではなく、サイト全体の“流れ”が評価されている。
この3つの構造ミスを修正できるかどうかで、
合否は大きく変わってくるんです。
合格のカギは“アクセス導線”にあった
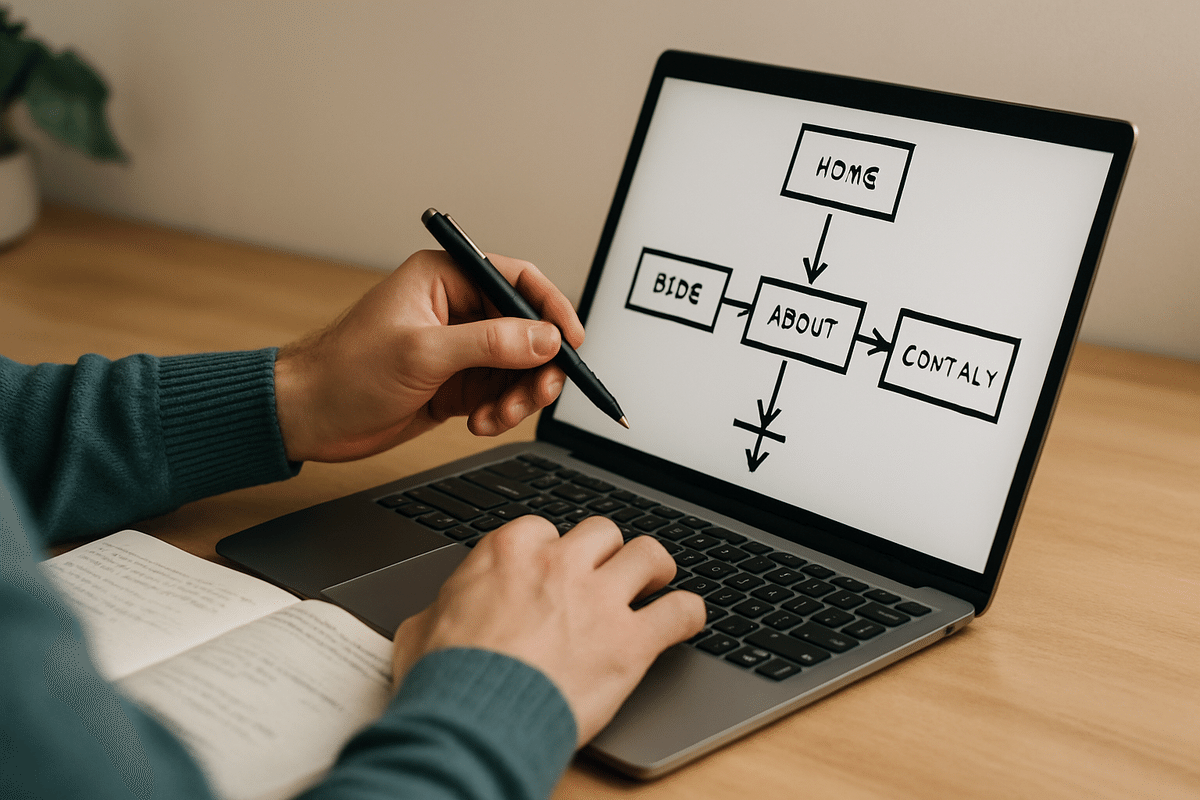
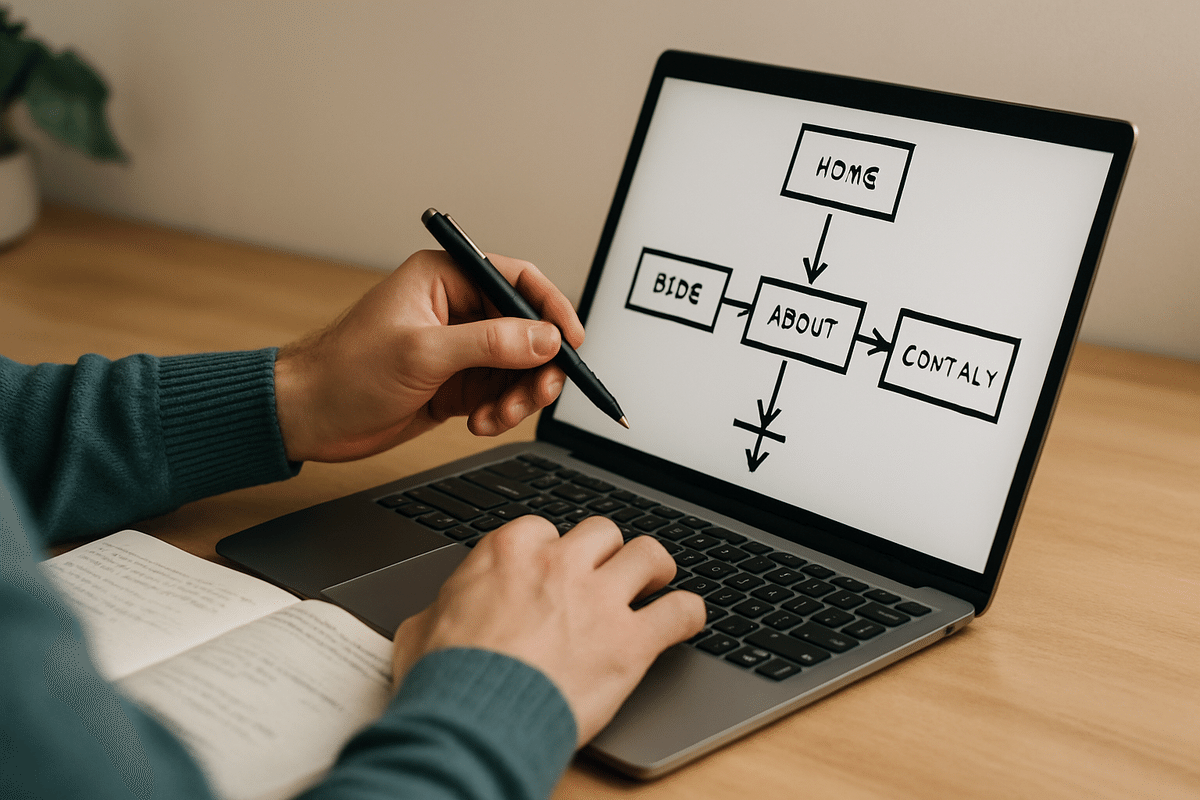
気づきを得てから、僕の視点は一気に変わりました。
それまでは「記事をどう書くか」ばかり考えていたのに、
本当に整えるべきは記事の外側の流れだったんです。
記事数を増やしても変わらない。
テンプレを守っても結果は同じ。
じゃあ、何が足りなかったのか?
答えはシンプルでした。
「読者がどこから来て、どこへ進むのか」・・・その導線設計だった。
僕は合格に至るまでの過程で、こんな問いを自分に投げかけ直しました。
✔ この導線は、誰に向けて設計しているのか?
✔ 記事同士に意味のある繋がりはあるか?
✔ 読者にどんな行動をとってほしいのか?
これを意識してブログを再設計していくと、
今までの「ただの記事の羅列」が、ひとつの“流れ”を持ったサイトへと変わっていきました。
そして、いざ再申請。
結果は・・・合格。
記事数は変えていません。
大幅なリライトもしていません。
やったのは、視点を変えただけ。
導線を整えただけで、結果は180度変わったんです。
この経験から僕は確信しました。
アドセンス審査において一番のカギを握っているのは、
記事のクオリティよりも、アクセス導線の設計力だと。
そしてその視点さえ持てれば、
今まで「落ち続ける理由が分からなかった」状態から抜け出せるんです。
「どこから来た誰を、どこへ導くか?」という設計の話
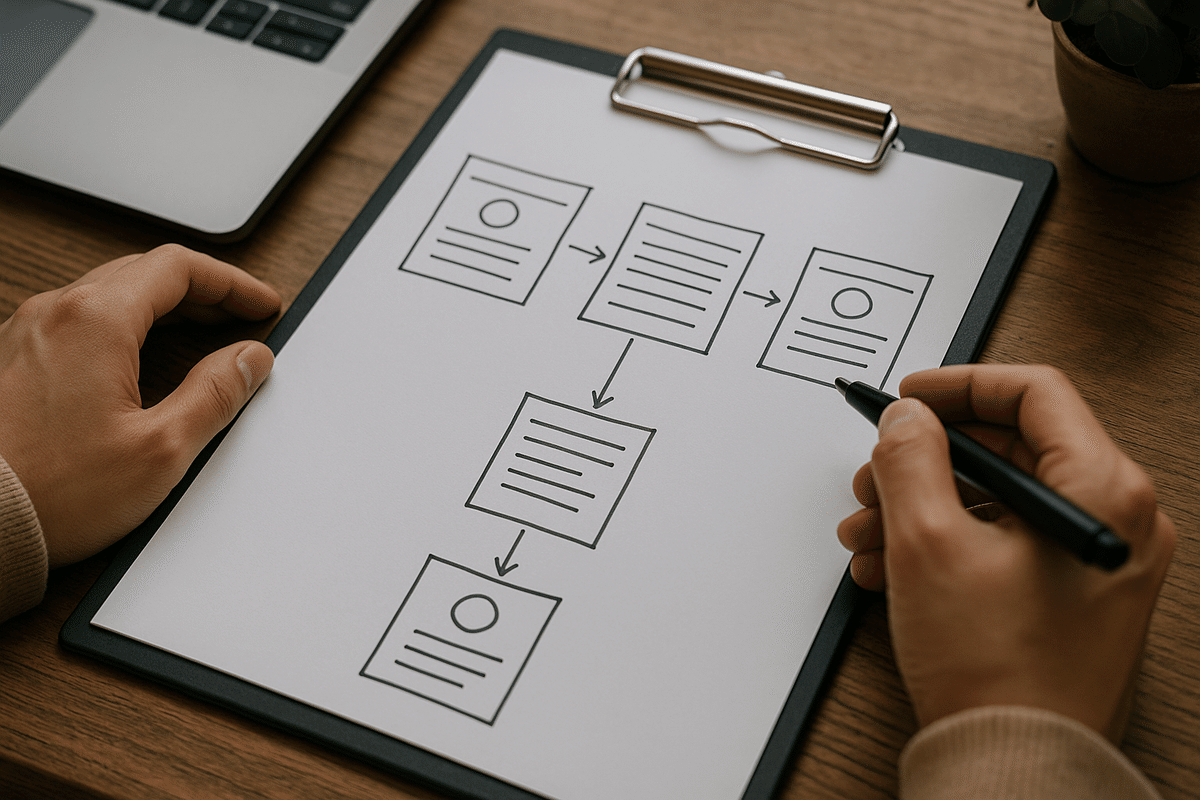
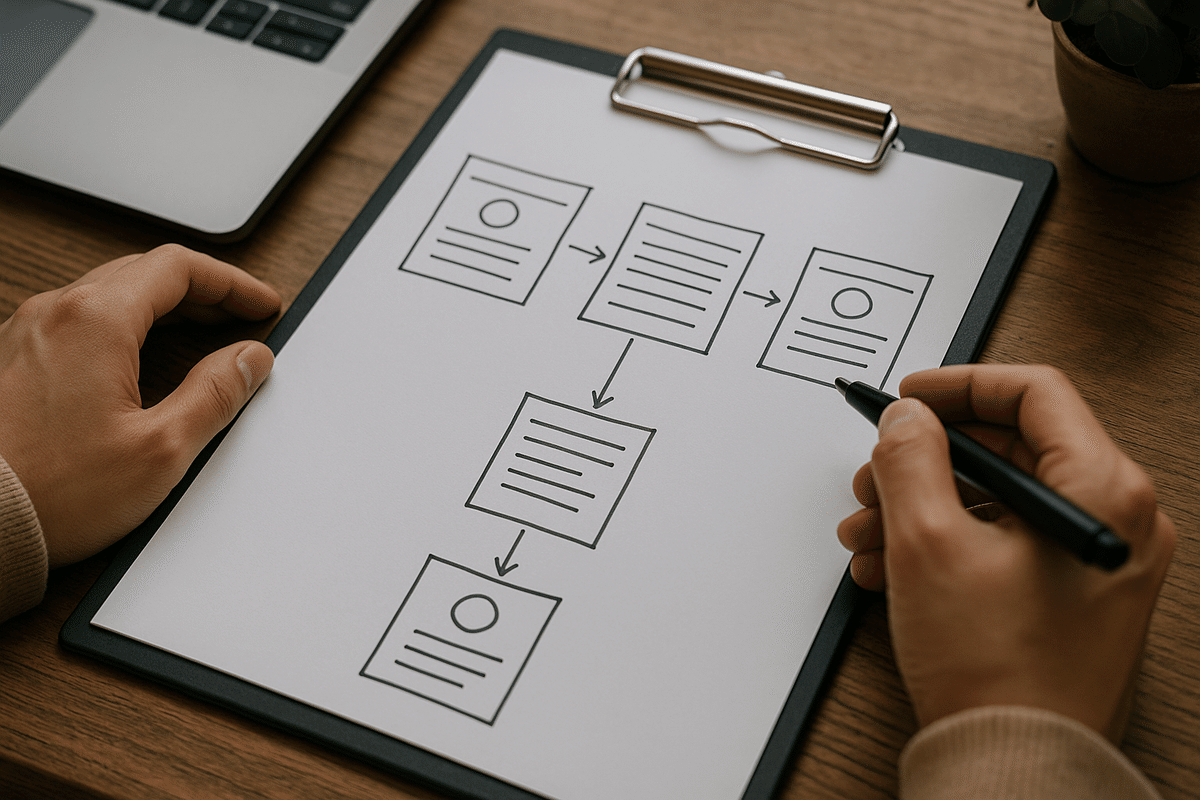
アドセンス審査を突破するうえで、
僕が最も強く意識するようになったのは、
「読者の動線を設計する」という視点でした。
記事をどう書くかよりも、
「誰がどこからやってきて、次にどこへ進むのか」を
徹底的に考える。
これが、今の審査に通るための“本質”なんです。
たとえば、検索から来た人がいるとします。
「その人は、どんな悩みを抱えてここにたどり着いたのか?」
「記事を読んだあと、どんな情報を欲しがるだろうか?」
この問いを明確にしておかないと、
記事同士がバラバラに存在しているだけになります。
そして、読者は行き場を失う。
それこそが“不合格の原因”になるんです。
逆に、導線が整っているサイトはどうか。
記事を読み終えた読者に、自然と次の記事が提示される。
記事同士にストーリー性がある。
「なるほど、次はこれを読めばいいんだ」と思える流れになっている。
このとき、ブログ全体が“1本の道”として機能し始めます。
審査で見られているのは「記事の点」ではなく「導線という線」なんです。
ここで重要なのは、
導線設計がただの“審査対策”で終わらないこと。
導線を整えることは、そのまま収益化の布石になります。
どこから来た読者を、どうやって次のアクションにつなげるか。
それを考えることで、
広告を貼る前から“商品につながる仕組み”が自然に出来上がっていきます。
つまり、アドセンス審査に合格するための視点は、
そのまま「合格後に収益を伸ばすための視点」でもある。
だからこそ、今この段階で
「どこから来た誰を、どこへ導くか?」を意識することが、
長期的に見ても大きな意味を持つんです。
3度目の合格体験で分かった、“見る場所”の違い
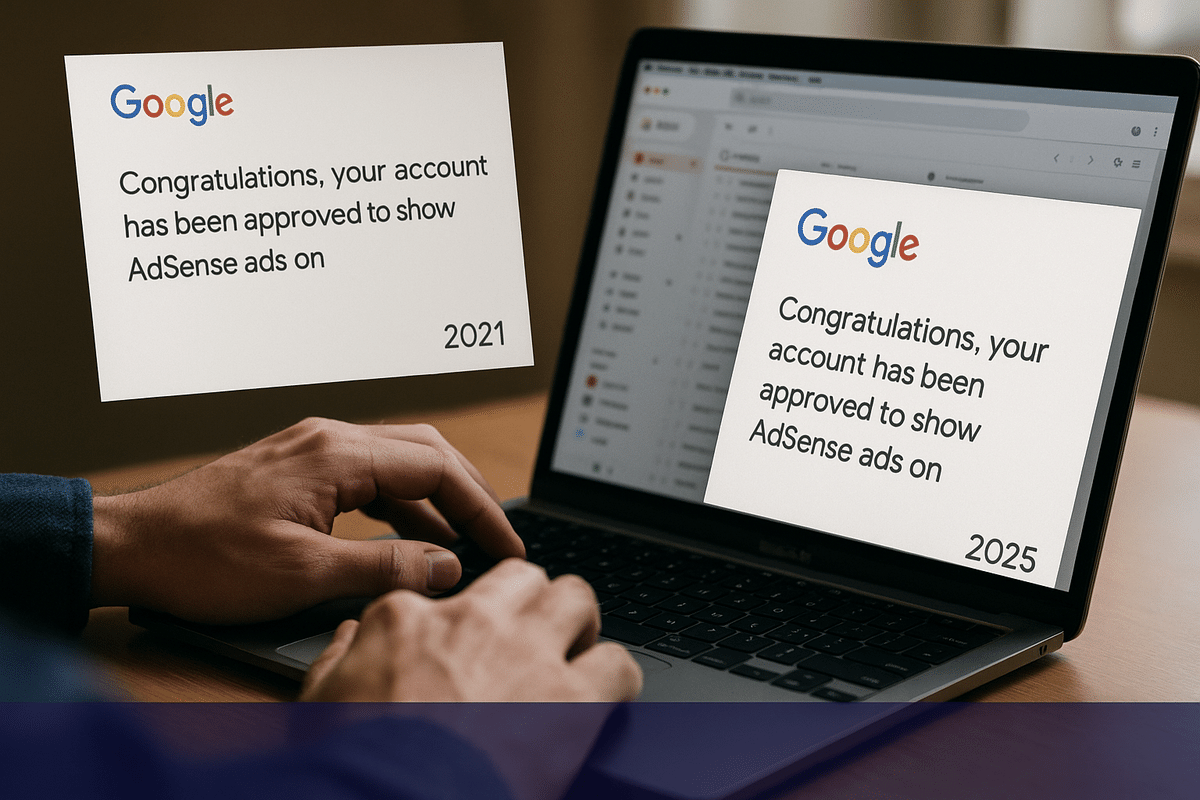
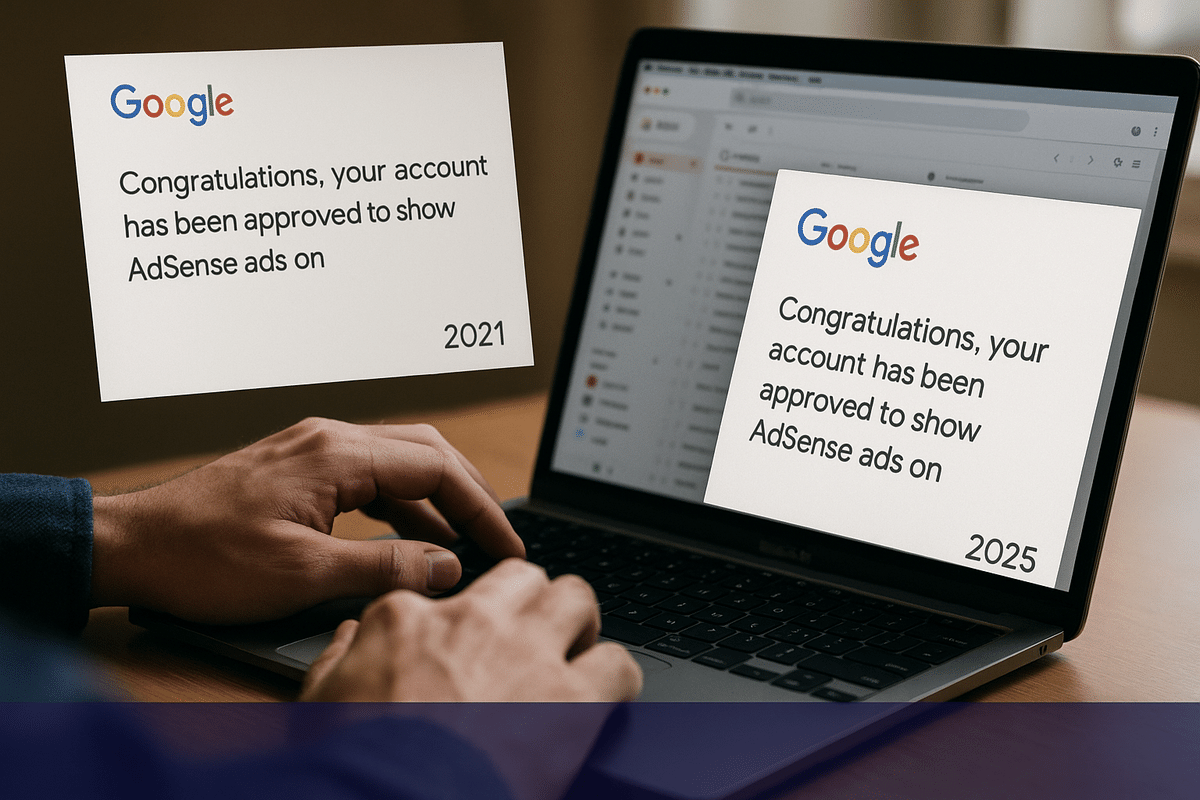
僕が実際に合格を掴んだのは、3度目の挑戦でした。
それまでと大きく変えたのは・・・記事数でもなければ、
デザインでもありません。
変えたのは、視点だけでした。
1度目と2度目は、典型的なテンプレ対策を徹底しました。
記事数を増やし、プロフィールを整え、
ポリシーページも漏れなく設置。
「これなら通るだろう」と思って申請したものの、
結果はどちらも不合格。
そのときの僕は、
「記事数がまだ足りないのかな?」とか
「もっと情報を詰め込まないとダメなのか?」とばかり考えていました。
でも、3度目の挑戦では違いました。
記事の数はそのまま。
内容も大きくはいじっていない。
ただ「導線設計」を徹底的に整えたんです。
・記事同士をストーリーでつなぐ
・読者が次に読むべき記事を分かりやすく配置する
・サイト全体に“ひとつの流れ”を作る
こうしてブログを“線”として設計し直した結果、
申請して数日後・・・初めて「合格」の通知が届いたんです。
このとき思ったのは、
「合格を分けていたのは努力量じゃなく、見る場所の違い」でした。
どれだけ頑張って記事を積み上げても、
導線という“骨格”がなければ評価されない。
逆に、そこを整えるだけで、
これまで不合格だったブログが一気に通過する。
「記事を足すこと」ではなく、「導線を描くこと」が合格の本質だった。
そして、この経験は僕にとって大きな財産になりました。
なぜなら、この視点は“審査突破”にとどまらないからです。
導線を意識してブログを作れば、
そのまま収益化の仕組みにつながっていく。
合格はゴールではなく、スタートに変わる。
3度目の挑戦で僕が得た最大の気づきは、
まさにこの「見る場所の違い」だったんです。
【設計図を公開】この記事が最後の挑戦になる人へ
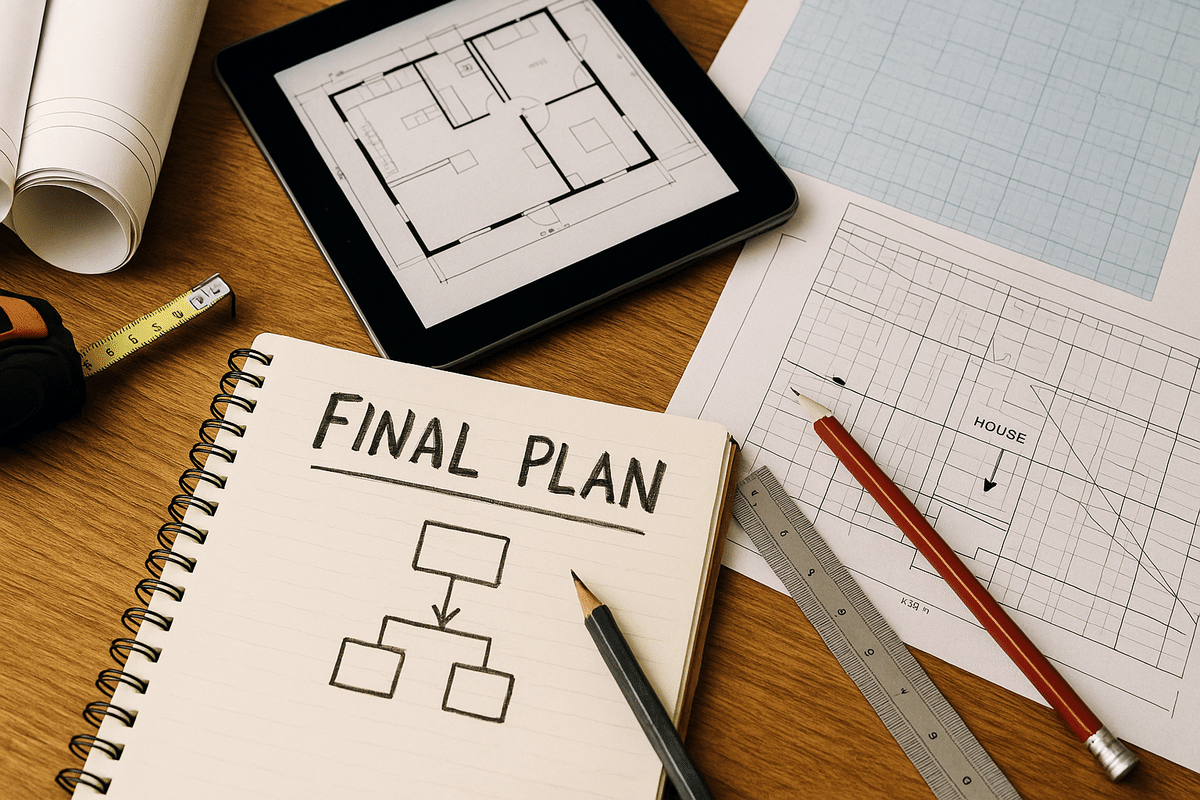
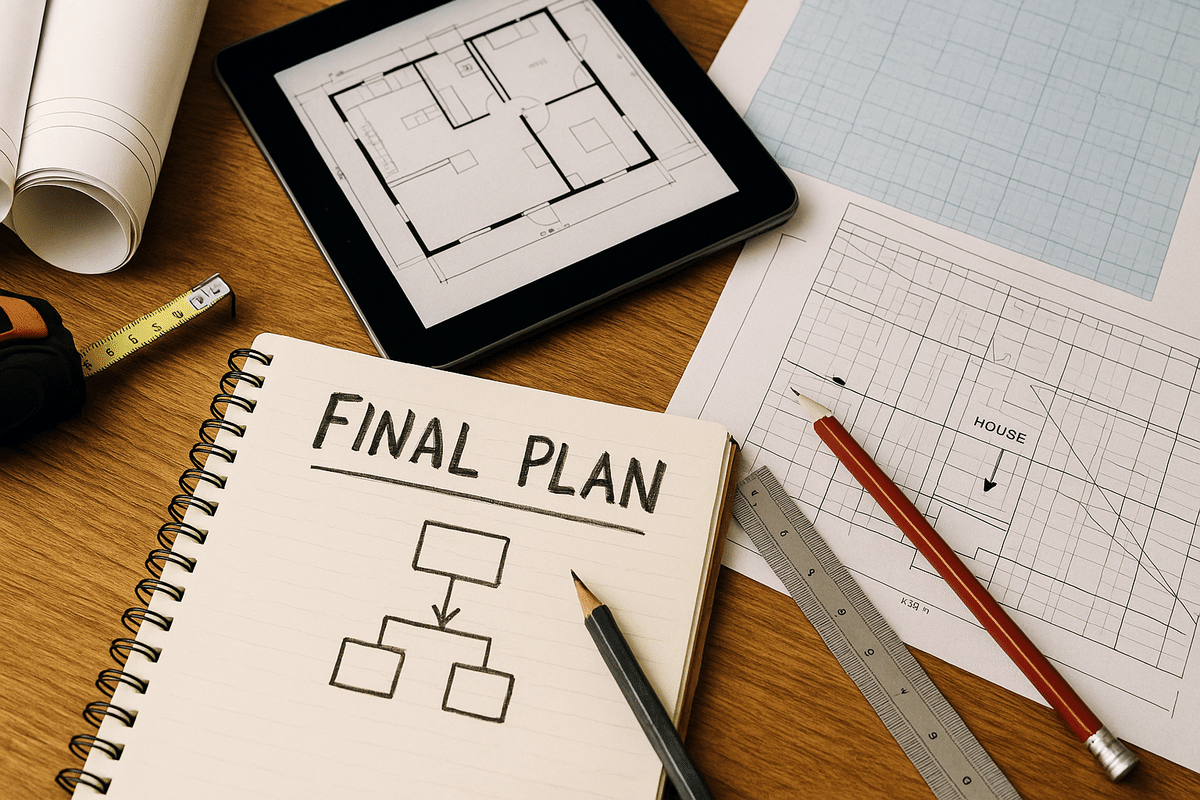
ここまで読んで「ハッ」とした人もいると思います。
僕が何度も不合格を繰り返しながら、
ようやくたどり着いたのは、
“導線”という視点でした。
記事の中身を磨くだけでは足りない。
大事なのは「誰を、どこへ導くか」という全体の設計。
そして、この視点を取り入れてから、
僕は3度目で合格を掴むことができました。
この記事ではその一部を無料で公開しましたが、
実際にはもっと具体的な設計手順があります。
✔ ChatGPTをどう活用して記事のベースを作るか
✔ 記事同士を“線”でつなぐ導線設計のやり方
✔ 合格後の収益化まで見据えたブログ構成の考え方
これらをすべて、
「突破の設計図」として有料記事にまとめました。
この記事は「体験談」ではなく「再現可能な戦略」です。
・テンプレを信じたけど通らなかった人
・記事数を増やしてもダメだった人
・ChatGPTを使ったのに落ち続けた人
そんなあなたのために、
型にはまらない“突破法”を具体的に言語化しています。
アドセンス審査は、
“見る場所を少し変えるだけで”結果が変わります。
今までの努力をムダにしないために。
そして、「また落ちた…」を最後にするために。
どうかこの記事を、
あなたの“最後の挑戦”のカギとして使ってください。
あなたの「不合格ループ」を終わらせるために
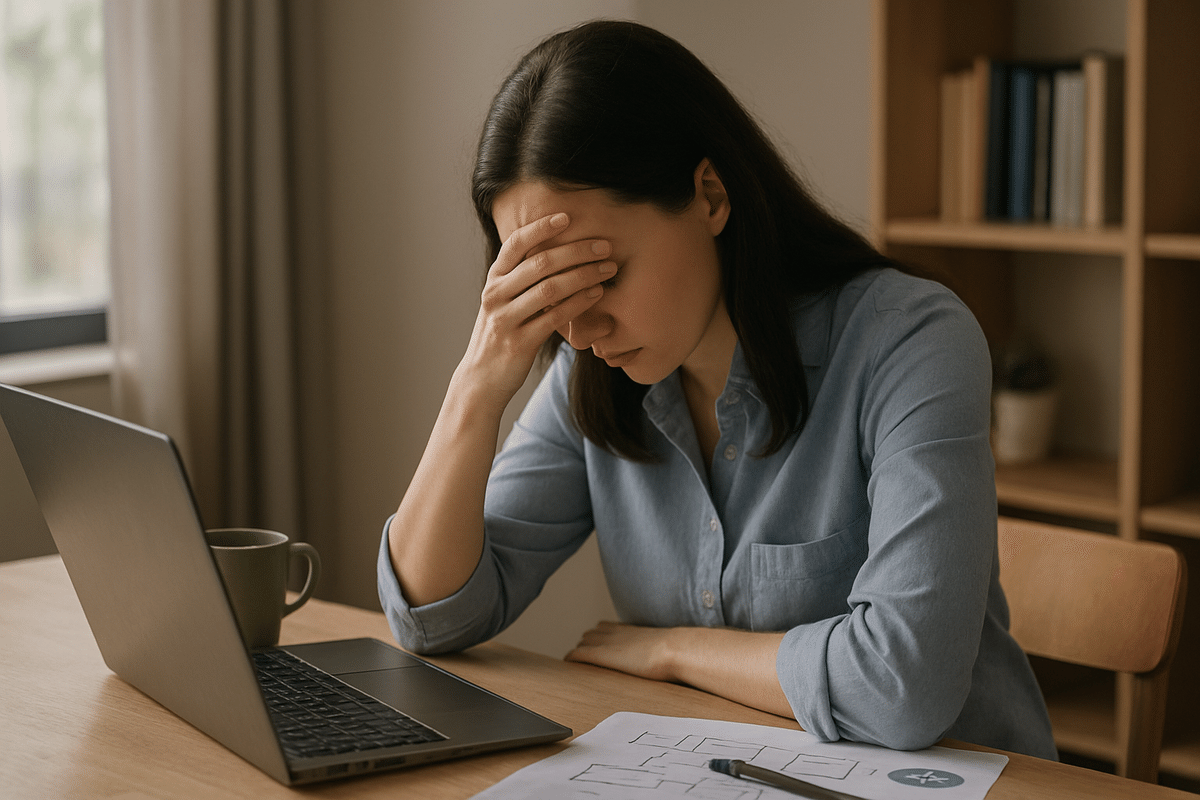
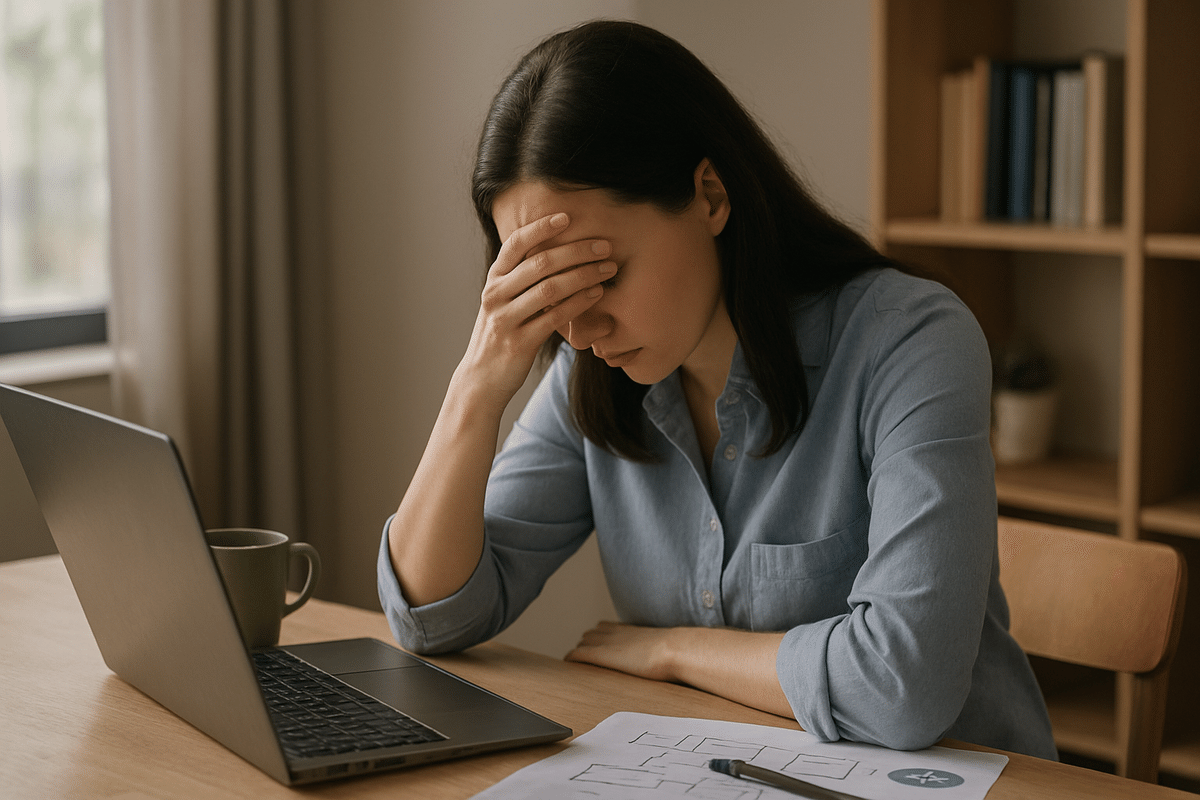
ここまでお伝えしてきた内容は、
あくまで“導入”にすぎません。
実際には、もっと具体的な手順や設計法があります。
それをすべて詰め込んだのが、今回の有料記事です。
✅ この有料記事で得られるもの
・審査に落ちる本当の理由を、戦略として理解できる
・今チェックされている“構造的なポイント”が明確になる
・「アクセス導線」という考え方を具体的に設計できる
・テンプレではなく、“仕組み”で合格を狙える
・合格の先にある収益導線まで視野に入れられる
✅ 価格について
この記事の価格は 1,500円 です。
正直に言うと、4回落ちればすでに1万円以上の損失。
記事削除や修正にかけた時間まで考えれば、もっと大きな損です。
だからこそ、1,500円の自己投資で、
不合格ループを抜け出せるなら安すぎると思っています。
✅ 僕が伝えたいこと
アドセンスに落ち続けるのは、あなたのせいじゃありません。
ただ「見るべき場所」を間違えていただけなんです。
そして、その視点を少しズラすだけで、結果は大きく変わります。
「合格」を掴むために必要なのは、記事数ではなく導線。
この考え方を持てば、審査を突破するだけでなく、
その後の収益化までも視野に入れられるようになります。
✅ 最後に
アドセンス合格はゴールではありません。
ここからが、あなたの武器になる。
「また落ちた…」と嘆いていた僕でも、
視点を変えるだけで突破できました。
だから今度は、あなたの番です。
この記事が、あなたの挑戦を「合格」へと導く
小さなカギになれば嬉しいです。
👇 今すぐチェックする
[突破の設計図|1,500円]